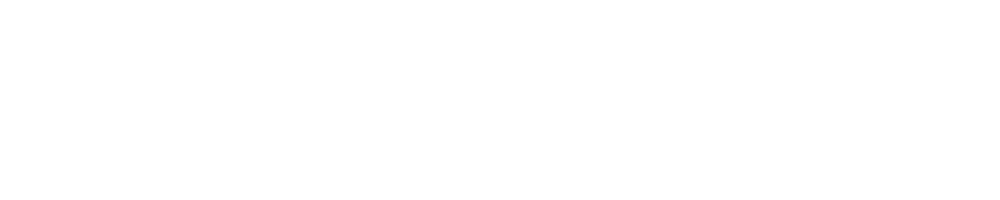20年ほど前の桜の咲くころ、近所の樹木公園を散策している際に、可愛らしい花を咲かせている植物を見かけ、写真に収めました。その写真を植物に詳しい上司に見てもらうと、ヤマエンゴサクの花と教えてくれました。当時、身近に生薬として利用している植物が自生していることに驚きました。その他にカタクリ、ショウジョウバカマ、イチリンソウなどの花も楽しみました。これらの植物は、早春に花を咲かせ、初夏には姿が消えてしまうことから、春の儚いもの、春の短命なもの、という意味で「スプリング・エフェメラル」と呼ばれています。しかし、実際は多年草であり、毎年可愛らしい花を咲かせています。主に落葉広葉樹林の林床に生息し、早春の樹木の葉が生い茂る前の短い期間の日差しを利用して光合成し、地下部にしっかりと栄養を蓄えています。樹木の葉が成長して日光が届かなく初夏になると、地上部が枯れて休眠状態に入ります。生薬の延胡索は、「日本薬局方」で、
Corydalis turtschaninovii Besser forma yanhusuo Y. H. Chou et C. C. Hsu(Papaveraceae)の塊茎を、通例、湯通ししたものであると規定されています。中国では畑で栽培されており、秋に植え付け、初夏に地上部が枯れた後に充実した塊茎が収穫されます。あの可愛らしい花の地下に、どのように地下茎が肥大しているのか確認してみたい、と思い続けていました。樹木公園で掘り起こすわけにもいかず、長い間気になっておりました。最近、前述の上司にそのことを話したところ、中国栽培地の写真を見せてもらいました。そこには立派な塊茎が連なっている様子が確認できました。
日本に自生しているエンゴサクでは、このような長く連なった塊茎はできず、大きさも小さいようですが、掘り起こして確認したい気持ちはまだ消えておりません。
延胡索は優れた駆瘀血作用と鎮痛作用があり、
これを配合する漢方処方には、芎帰調血飲第一加減、安中散、折衝飲があります。
ご活用いただければ幸いです。
(コタロー通信 613号)
延胡索について・・・コタロー通信
 お知らせ
お知らせ